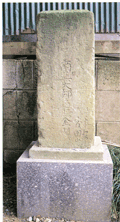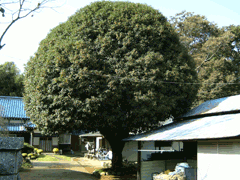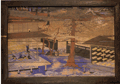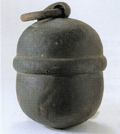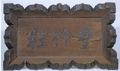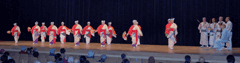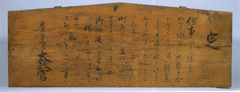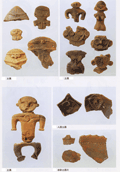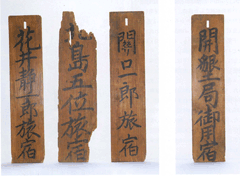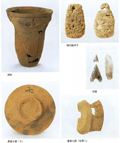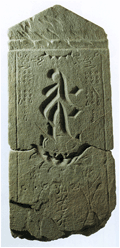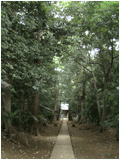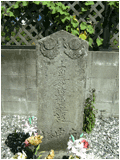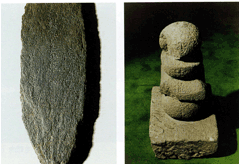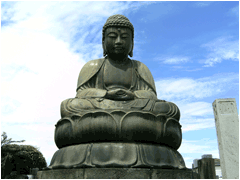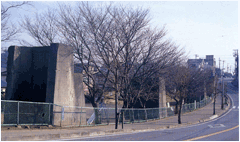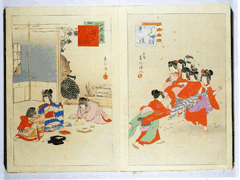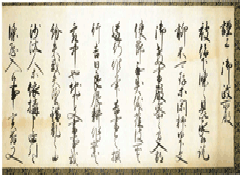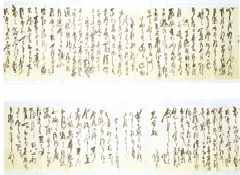鎌ケ谷市の文化財
更新日:2020年10月21日
- マップに示した位置は正確な位置を示していない場合もあるので、お問い合わせください。
| 【遺跡】 佐津間城跡(さつまじょうあと) | |
|---|---|
| 中佐津間1-9 佐津間城跡は東側に大津川をのぞむ標高25メートルの台地上に築かれており、台地下の集落とは約9メートルの比高がある。土塁と空堀をめぐらせて、周囲を台地から遮断して郭を形成する単郭構造の城郭である。守備を主体としたようで、四方に張り出した構造の櫓台と、その櫓台を利用した横矢構造(注釈1)が確認され、郭の入口となる虎口(注釈2)の跡も残っている。また、こうした入口が村落側にあることは、城と村落が一体の関係であったことも推定される。城の大きさは堀の外側で東西50メートル、南北76メートル、土塁の内側で東西21メートル、南北35メートルある。周囲には屋敷裏、北根郷屋、南木戸などの城に関係する小字名も残っている。 築造された時期は戦国時代(16世紀中から後半頃まで)と推定されている。 [注記] 注釈1 侵入する敵を側面から攻撃できる構造。 |
|
| 【石造物】 光明真言道標(こうみょうしんごんどうひょう) | |
|---|---|
| 南佐津間10 (詳しい場所はお問い合わせ下さい) 北部公民館から宝泉院に向かう路傍に所在する。密教の呪文である24字の梵字(古代インドの文字)からなる光明真言を円形に連ね、中央に大日真言(注釈1)を配している。また、鮮魚道の道標を兼ねており、正面に「木おろし 成田山道」、右側に「松戸 江戸道」、左側に「粟野 ふなばし道」とある。文久4年(1864年)の造立である。 なお、鮮魚道は我孫子の布佐から松戸を結んだ道である。銚子で水揚げされた魚を江戸まで運ぶルートにあたるためそう呼ばれた。 [注記] 注釈1 すべての功徳を得るため唱えられるもの。翻訳せず原語のままで唱えられるため梵字で書かれている。 |
|
| 【石造物】 渋谷総司贈位顕彰碑(しぶやそうじぞういけんしょうひ) | |
|---|---|
| 南佐津間9-37 (宝泉院境内) 渋谷総司は佐津間出身の討幕勤王の志士である。赤報隊(新政府軍先鋒隊)に参加し、年貢半減をかかげて東山道を進軍し活躍した。しかし「偽官軍」の汚名を着せられ、慶応4年(1868年)、隊長であった相楽総三らとともに下諏訪で斬首された。この時、総司は22歳であった。 なお、「偽官軍」として処刑された者に対する祭祀は、遺族も世をはばかり思うようにできなかったが、明治3年には処刑された地に「魁塚」と名付けられた塚が建立された。大正から昭和初期にかけて赤報隊員たちの名誉回復運動が行われ、数度の請願の結果、昭和3年(1928年)復権し、贈位を記念してこの碑が建てられた。 |
|
| 【市指定文化財】 北方前板碑(ぼっけまえいたび) | |
|---|---|
| 個人蔵、郷土資料館寄託(中央1-8-31) 板碑は石製の供養塔である。市内の板碑は、埼玉県北西部で採掘された緑泥片岩を用いた武蔵型板碑が多い。北方前板碑は元徳3年(1331年)を最古に35基の板碑がある。すべて阿弥陀如来を表わす梵字( 昭和53年1月指定 |
|
| 【市指定文化財】 キンモクセイ(きんもくせい) | |
|---|---|
| 粟野(個人宅内) キンモクセイは市木として親しまれている。この木は高さ約8メートル、胸高直径約55センチメートルの木である。市内にはキンモクセイが多く、この木は市内一の大木である。毎年10月初旬ころ、オレンジ色の小さな花を多数つけて豊かな芳香を放つ。 昭和60年9月指定 |
|
| 【市指定文化財】 粟野庚申講・粟野庚申塔群(あわのこうしんこう・あわのこうしんとうぐん) | |
|---|---|
| 粟野208 (八坂神社境内) (詳しい場所はお問い合わせ下さい) 中国の道教の教えを根源とする庚申信仰は、人の体内にいるとされる「三尸の虫」が60日毎の庚申の夜、寝ている間に天に上って天帝にその人の日頃の悪事を報告し、命を縮められるというもので、庚申講はそれを防ぐため、庚申の夜は眠らずにいれば、早死にせずに長生きできるという民間信仰である。庚申塔は江戸時代には盛んに建てられたが、明治時代以降は次第に少なくなる。 粟野は、江戸時代前期から現代まで庚申講が続いている市内で唯一の地区である。現在は夜通し行う講は行われていないが、講による庚申塔の造塔が継承されている。ここに造立された庚申塔は、元禄12年(1699年)が最も古い。文化12年(1815年)以降(1845年と1850年をのぞく)は5年ごとに現在まで規則正しく建てられている。 なお、八坂神社は、明治12年(1879年)頃に千葉県が作成した「神社明細帳」によると、大永3年(1523年)の創立とされている。 |
|
| 【石造物】 粟野の石塔群(あわののせきとうぐん) | |
|---|---|
粟野208 (八坂神社境内)他 (詳しい場所はお問い合わせ下さい) |
|
| 【市指定文化財】 手洗鉢(ちょうずばち)・額「絵馬」・鈴(すず)・額 「豊作社」(ほうさくしゃ) | |
|---|---|
初富221-1 (豊作稲荷神社) |
|
| 【石造物】 孝心講建設の道標 (こうしんこうけんせつのどうひょう) | |
|---|---|
| 軽井沢2082 (詳しい場所はお問い合わせ下さい) 軽井沢集会所横の信号付近に所在する。軽井沢字清水の旧鮮魚道に建てられた道標で、鎌ケ谷村・旧佐津間村・旧初富村などの地名が刻まれていることから、明治22年(1889年)以後の建立と推測される。孝心(富士)講の人たちが道普請の時に建てたものと思われる。 富士講は富士山を信仰し、登拝するもので、庚申信仰と結びつけて「庚申」の教えを「孝心」に置き換え、江戸時代に盛行した。孝心講はその流れをくむもので、全く無償の土木奉仕活動などを行っていた。 | |
| 【市指定文化財】 おしゃらく踊り(おしゃらくおどり) | |
|---|---|
| 軽井沢地区 軽井沢地区に伝えられる。お化粧をし、派手な長襦袢やきれいな着物を着て踊ることから、「おしゃれ」がなまって「おしゃらく」となったといわれている。小道具として手拭(豆絞り)や扇を使う。摺り鉦と締め太鼓、三味線による伴奏で「高砂」「木更津」などの唄に合わせて、手踊りするものである。戦前までは小念仏踊りともよばれ、念仏講に由来する関東地方発祥の代表的な農民芸能の一つで、江戸中期以降に旅芸人などを介して流行し、幕末から明治期にかけて盛行して、結婚式などめでたい席で演じられた。厳しい農作業に明け暮れた生活の中での娯楽のひとつとして、活気に満ち溢れた当時の暮らしの様子を今に伝える貴重な無形民俗文化財である。 市内では、かつて木下街道沿いの鎌ケ谷地区にも残っていたが、現在は軽井沢地区のみに残っており、鎌ケ谷市おしゃらく踊り保存会(昭和58年1月結成)により、保存、継承、普及活動が行われており、昭和61年12月に鎌ケ谷市の無形民俗文化財に指定されている。県内で同じ系統の踊りとして松戸の万作踊り(県指定)、浦安のお洒落踊り(県指定)などがある。 昭和61年12月指定 | |
| 【石造物】 庚申道標(こうしんどうひょう) | |
|---|---|
| 軽井沢2009 (詳しい場所はお問い合わせ下さい) 軽井沢字落山の路傍に所在する。青面金剛(注釈1)を表す梵字( 右側面には「東 志ろ井(白井) 軽井沢」、左側面には「南 かまがや 北 ふじがや」などとあり、鮮魚道の重要な道標でもあったことがうかがえる。 [注記] 注釈1 庚申講の本尊。三尸の虫を抑える神とされている 注釈2 象形文字のようすを色濃く残す古書体のひとつ | |
| 【遺跡】 東林跡遺跡(ひがしはやしあといせき) | |
|---|---|
| 初富803他 東林跡遺跡は初富の第五中学校建設時に調査された旧石器時代の遺跡で、市内で発見されている最古の遺跡のひとつである。当時は氷河期の終わり頃にあたり、平均気温が今より5、6度低く、鎌ケ谷市周辺の様子は草原や針葉樹の林が広がっていたようある。土器の使用は始まっておらず、発見されるのは石器だけである。旧石器時代遺跡の調査では石器や石器の製作途上に生じる剥片(フレイク)、石くず(チップ)が集中して出土することが多く見られ、このような遺物集中出土地点を「ブロック」などと呼ぶ。 東林跡遺跡の主体となる「ブロック」は17ヶ所発見されている。旧石器時代は狩りが中心の移動生活で、住まいは簡易テントのようなものであったと考えられており、これらの「ブロック」は当時の人々の行動を推測できる数少ない手がかりとなる。また、これらの「ブロック」は2万5千から2万9千年前までに大噴火したと推定されている、九州の鹿児島湾付近にあった姶良カルデラを噴出源とする姶良Tn火山灰より下の地層で確認されていることから、この遺跡はそれ以前に形成されたものと推測される。 写真は槍の先や物を切るために使われたと考えられるナイフ形石器等である。 | |
| 【国史跡】 下総小金中野牧跡(野馬土手)(しもうさこがねなかのまきあと(のまどて)) | |
|---|---|
| 東初富1-20 江戸幕府は、軍馬を確保するため下総地方に小金牧・佐倉牧を設置した。市域の台地上のほとんどは小金五牧のうちの中野牧に属した。牧では最盛期には1,000頭もの野馬が野放し飼いにされ、通常は餌などが与えられないため、野馬が村に入り畑の作物を食い荒らすこともあった。そのため、村人は野馬が入ってこないように村と牧との境に野馬除けの土手を築いた。また野馬を水呑み場や捕込へ効率的に誘導するための土手(勢子土手という)が築かれた。これらを合わせて野馬土手とよぶ。なお、勢子土手は幕府の手当てにより作られたが、野馬除土手の築造、補修はすべて村の負担で行われたという。かつて野馬土手は市内各所に所在していたが、開発等に伴い年々減少してきている。そこで、永く保護・保存するためにこの初富小学校校庭横に所在する野馬土手は捕込と共に国史跡に指定された。この野馬土手は勢子土手と呼ばれる種類の野馬土手である。 平成19年2月6日指定(国史跡) | |
| 【国史跡】 下総小金中野牧跡(捕込)(しもうさこがねなかのまきあと(とっこめ)) | |
|---|---|
| 東中沢2-1 江戸幕府が軍馬需要をまかなうため、直轄して設置した小金牧の1つの中野牧の遺構である。捕込は、野馬を追い込み、捕らえて選別する施設である。捕えられた野馬のうち、三歳馬は乗用に養成されたり、周辺の住民の労働力を荷うものとして払い下げられた。それ以外の馬は再び野に放されたが、この年に生まれた当歳馬については他の牧の馬と区別するための焼印が尻に押された。焼印は牧ごとに印が決まっており、中野牧は千鳥の印であった。なお、野馬の売払い金は少ないながらも幕府の安定した収入となった。年に1回行われた野馬捕りでここに野馬を追い込むのは、周囲の村々から集められた勢子の仕事であった。野馬捕りの様子は勇壮だったようで、江戸からも多くの見物客が訪れる重要な年中行事であった。中野牧の捕込は小金牧の中で、唯一現存しているもので、元は三つあった区画のうちの一区画がそのまま残っている。 江戸幕府の軍事力を支えた軍馬生産を知る上で重要であることから、平成19年2月6日に国史跡に指定された。 |
|
| 【市指定文化財】 土地紀念講碑(とちきねんこうひ) | |
|---|---|
| 北初富6-1(光圓寺境内) 初富開墾 は牧の 廃止後 、江戸での仕事を失った人々を 救済 するために明治2年(1869年)から始まった。しかし、当初の 入植者 には元武士や町人など農作業に慣れていない者が多かった上に、作物の不作が重なったため、多数の 離散者 が出たり、開墾会社と開墾人との間で土地の取り扱いについて土地 騒動 が起こるなど困難をきわめたものであった。その後、近隣の村々から移住してきた農家出身者も加わり、苦しい中でも徐々に開墾を成功させていった。その子孫が集まり、当時の生活を忘れないように 芋粥 をすすって 祖先 をしのび、励まし合ったのが土地紀念講である。この碑は開墾50周年を記念して、大正7年(1918年)に光圓寺境内に建てられたものである。 昭和50年1月指定 |
|
| 【市指定文化財】 制札「慶応四年太政官布告」 (せいさつ「けいおうよねんだいじょうかんふこく」 ) | |
|---|---|
| 個人蔵及び中央1-8-31(郷土資料館) 慶応4年(1868年)、明治政府は「五箇条の御誓文」を発布した。一方庶民に対して「五蒡の掲示」を出し、江戸時代と同様に、一揆やキリスト教を禁止した。この制札は、道野辺の妙蓮寺わきの路傍に立てられたといわれている。 写真の制札は横103センチメートル、縦(最大)51.7センチメートル、厚さ3.5センチメートルの杉板製である。 昭和52年7月指定 | |
| 【遺跡】 中沢貝塚(なかざわかいづか) | |
|---|---|
| 東中沢2-10 他 貝柄山公園西側の台地上にある直径約130メートルの馬蹄型貝塚で、市内では最も大きく、県内でも規模・内容とも有数の貝塚である。昭和30年代後半から30次近い調査を行った結果、多数の住居跡が発見されている。また、出土品として大量の土器・石器の他、土偶をはじめとする特殊な遺物も数多く出土している。土偶などは祭祀に使われていたと考えられており、精神生活も豊かで多様であったことがうかがえる。貝層からは動物の骨なども多数発見されているため、海産資源の活用とともに狩りも盛んに行われていたことがわかる。石器では弓矢の先に付けられた石鏃のほか、打製石斧、磨製石斧、石皿、磨石等も数多く出土しており、土の掘り起こしや木の伐採(打製石斧・磨製石斧)や、木の実などの採集(石皿・磨石による木の実の皮むき、磨りつぶし)もしていたことがうかがえる。なお、この遺跡が形成されたのは、発見された遺物などから縄文時代後期(約4千から3千年前まで)を中心に、中期から晩期(約5千から2千3百年前まで)に及ぶと推測される。 写真は中沢貝塚から出土した土偶である。土偶は豊穣や病気の回復を祈るまじないに使われたと考えられ、壊れた状態で出土するものがほとんどである。下段右側の人面土器は土器の内側に人の顔が表現された珍しいものである。 | |
| 【市指定文化財】 下総牧開墾局知事(しもうさまきかいこんきょくちじ)北島秀朝等(きたじまひでともら) 旅宿看板(りょしゅくかんばん) | |
|---|---|
| 中央1-8-31 (郷土資料館) 下総牧の開墾事業が始まる直前の明治2年(1869年)に東京府開墾局知事北島秀朝ら開墾局の役人たちが、当時粟野村の名主を務めていた渋谷家に宿泊し、実際に開墾予定地を視察したことを示すものである。最初の開墾地となるこの地が豊かな土地になるようにと願いを込め、この地で「初富」と命名・宣言したされる史実を具体的に裏付けるとともに、開墾開始前後の資料は皆無に近いため、極めて貴重な資料である。 看板には北島の名前とともに同行した開墾局の役人の名前などが墨書きされている。 写真左「花井静一郎旅宿」(表)・「開墾局御用宿」(裏 右端)、写真中央「北島五位旅宿」(表裏とも)、写真右「関口一郎旅宿」(表・裏記載なし) 北島の看板は杉材、他2点は桧材、大きさは3点とも概ね63センチメートル、幅14センチメートル、厚さ1センチメートルである。なお、北島は当時の位階で書かれている。 平成10年11月指定 | |
| 【遺跡】 大堀込遺跡(おおほりごめいせき) | |
|---|---|
| 中沢1123他 (詳しい場所はお問い合わせ下さい) 第四中学校を囲むように広がる縄文、古墳、奈良・平安時代に及ぶ複合遺跡である。各時代にわたり、住居跡などの遺構や遺物が発見されている。 写真は縄文時代の深鉢形土器、漁撈に使われたと考えられる軽石製の浮子、弓矢の先に付けられた石鏃、祭祀に用いられたと思われる土偶、奈良・平安時代の土師器に墨で「七」と書かれた墨書土器である。 | |
| 【遺跡】 根郷貝塚(ねごうかいづか) | |
|---|---|
| 中沢471他 (詳しい場所はお問い合わせ下さい) 万福寺の北側に位置する縄文、古墳、奈良・平安、室町時代に及ぶ複合遺跡である。各時代にわたり住居跡などの遺構や遺物が発見されている。特に縄文時代の住居跡には貝塚が残され、埋葬された状態で人骨が発見されている。 |
|
| 【遺跡】 万福寺境内遺跡(まんぷくじけいだいいせき) | |
|---|---|
| 中沢484 (万福寺境内) 152基以上の板碑と火葬人骨・骨壷・渡来銭などが出土した県内でも貴重な 中世遺跡である。弘安7年(1284年)の板碑が最古。梵字を刻んだ種子板碑と「南無妙法蓮華経」を刻んだ題目板碑とがあり、浄土教系(種子板碑)の信仰から日蓮宗(題目板碑)への改宗があったことがわかる。 | |
| 【市指定文化財】 八幡春日神社の森(はちまんかすがじんじゃのもり) | |
|---|---|
| 中沢907 (詳しい場所はお問い合わせ下さい) もともとスギとクロマツの人工林から始まり、約200から300年を経過しているものと思われる。胸高直径3メートル以上の巨木は、スギが2本、ムクノキが6本ある。 また、暖帯林特有のヤブツバキが亜高木として森をおおい、12月初旬ころから花が咲き始める。 平成4年8月指定 | |
| 【市指定文化財】 三橋家墓地(みはしけぼち)(歴代墓石含む) | |
|---|---|
| 中沢646 (詳しい場所はお問い合わせ下さい) 三橋家は、江戸時代に小金中野牧の牧士役をつとめた家柄である。牧士は野馬の管理を行ない、野馬捕りや将軍の鹿狩りの際には、勢子人足たちを指揮した。また、苗字帯刀の他、乗馬や鉄砲の所持も許されていた。この墓地には享保8年(1723年)に亡くなった五郎兵衛から、昭和の初めに貴族院議員として活躍した三橋彌まで、10代にわたる墓石がある。 昭和52年7月指定 | |
| 【石造物】 題目庚申道標(だいもくこうしんどうひょう) | |
|---|---|
| 中沢197 (詳しい場所はお問い合わせ下さい) 中沢字新橋の路傍にある。享和3年(1803年)に建てられ、髭文字(注釈1)で題目「南無妙法蓮華経」が刻まれている。庚申塔と道標も兼ね、 「右 か祢が崎(金ヶ作) 南 船ばし(橋)道 左 行とく(徳)」と刻まれているが、現在はもと建てられていた位置とずれている。 [注記] 注釈1 文字の端を髭のようにのばして書いた文字 | |
| 【市指定文化財】 妙蓮寺板碑及び五輪塔(みょうれんじいたびおよびごりんとう) | |
|---|---|
| 妙蓮寺 (常時公開はしていません) 妙蓮寺は中山法華経寺の末寺の古い寺である。道野辺は、日蓮の母妙蓮の生まれたところとの伝承もある。板碑には永享4年(1432年)の銘があり、「右為妙蓮逆修(注釈1)也」と刻まれている。五輪塔は石が5段に重ねられたもので、年代は不明。高さ45センチメートル。 昭和52年7月指定 [注記] 注釈1 逆修:自分の死後の幸福を願い、自ら(板碑を)造立すること。 | |
| 【石造物】 馬頭観音(ばとうかんのん) | |
|---|---|
| 道野辺35 他 (詳しい場所はお問い合わせ下さい) 馬は、動力機関が発達する近代以前には運輸や大きな労働力として貴重な存在であり、大切に扱われていた。そこで馬を飼育する人々の間で馬の無病息災や供養のために馬頭観音に祈願する講ができたりして、馬頭観音を造立することが広まった。市内では粟野の八坂神社に安永8年(1779年)銘のものが、現在確認されている中では最も古い。明治以降は次第に特定の日付が刻まれているものが多くなり、馬の墓標として造立されるようになったようである。 道野辺字下西山の墓地には、3基現存している。これらのうち、明治43年(1910年)造立のものは、日露戦争に徴発されて死んだ馬の供養のための馬頭観音である。 | |
| 【市指定文化財】 根頭神社の森(ねずじんじゃのもり) | |
|---|---|
| 道野辺49 (詳しい場所はお問い合わせ下さい) 市民の森の主要部分を占めている森で、スギ・ヒノキ・アカガシ・コブシなどの本殿林と、それを囲むスギ・ヒノキの人工林で構成されている。また、胸高直径3.48メートルのスダジイの巨木もある。スギの樹齢は100±10年と推定される。 また、草本類の種類も多く、ウラシマソウ、チゴユリ、ミヤマナルコユリ、ヤマユリ、ヒトリシズカなど多くのものが確認されている。 平成4年8月指定 | |
| 【市指定文化財】 魚文の句碑(ぎょぶんのくひ) | |
|---|---|
| 東鎌ケ谷1-7 「ひとつ家へ 人を吹き込む 枯野かな 魚文」(銘文)松尾芭蕉の流れをくむ俳人三級亭魚文が、旅の途中で鎌ケ谷宿を通った時に詠んだ句と思われる。「明和元年(1764年)、武陽産高橋氏建立」とある。木下街道の道標を兼ね、「右 木をろし道」「左 中木戸道」と刻まれている。 木下街道は古くは木下河岸と行徳河岸を結ぶ輸送路として、その後も江戸から鹿島方面への参詣や銚子方面へ向かう人々で賑わい、鎌ケ谷宿にも多くの文人墨客が往来していた。古くは松尾芭蕉が弟子を伴い「かしま紀行」を残している(貞享4年(1678年))。また、渡辺崋山は文政8年(1825年)に鎌ケ谷宿付近で「四州真景図」の「釜原」を描いている。鎌ケ谷市役所1階ロビーにはこの絵を模した壁画がある。 昭和47年3月指定 | |
| 【市指定文化財】 官軍兵士の墓(かんぐんへいしのはか) | |
|---|---|
| 鎌ケ谷1-5 (大仏墓地内) 慶応4年(1868年)、江戸幕府の滅亡に反発した旧幕府軍の一部と鎮圧に向かった新政府軍とが、市川・船橋周辺で激しい戦いをした。その折、鎌ケ谷大新田付近で、新政府軍側の佐土原藩(現宮崎県宮崎市佐土原町)の士分1名(俗名 蓑毛次右衛門)と兵糧方1名(俗名 巳之助、兵糧を輸送した農民と思われる)が戦死した。ここにはその当時、佐土原藩の弔い料により建てられた墓石と明治19年(1886年)に新政府軍側の戦死者に対して千葉県の官費で建てられた墓石がある。 この新政府軍と旧幕府軍の戦争による死傷者の数はわかっていない。新政府側の兵士の墓はこのようの所々で確認できるものの、旧幕府軍の戦死者は、当時、墓石に名前を刻むことすら難しかったため、ほとんど確認できない状態である。しかし、下総地方には幕府直轄の牧場があったなど旧幕府軍に与する傾向があり、一部で脱走様と呼ばれる旧幕府軍兵士の墓と思われるものも存在する。 昭和47年3月指定 | |
| 【市指定文化財】 鎌ケ谷大仏(かまがやだいぶつ) | |
|---|---|
| 鎌ケ谷1-5(大仏墓地内) 安永5年(1776年)、鎌ケ谷宿の大国屋(福田)文右衛門が、祖先の供養のために、江戸神田の鋳物師に鋳造させたもの。高さ1.8メートルの釈迦如来座像である。開眼供養には僧侶50人あまりを請じ、江戸の高級料理屋八百膳で300人前の料理を用意し、当時「つぼに白金、お平にゃ黄金、皿にゃ小判でとどめ刺す」と唄い囃されたと豪勢な様子が伝えられ、鎌ケ谷宿の盛時の有り様がうかがえる文化財である。 昭和47年3月指定 | |
| 【市指定文化財】 百庚申(ひゃくこうしん) | |
|---|---|
| 鎌ケ谷1-6 (八幡神社境内) 八幡神社境内に、天保12年(1841年)から13年までにかけて建てられた。青面金剛像が10基あり、その間に文字塔(「庚申塔」)が9基ずつの90基と合わせて100基ある。石塔(石像)を同じ場所に多く造立して、多くの功徳を得るため、100基という多数が建てられたものである。江戸時代後半に下総で流行した信仰形態である。 昭和63年12月指定 | |
| 【市指定文化財】 庚申道標(こうしんどうひょう) | |
|---|---|
| 鎌ケ谷1-6 (八幡神社境内) 元は、大仏十字路付近にあった庚申塚上に所在していたもの。中央の1基は寛政7年(1795年)に造立されたもので、側面には 「東 さくら(佐倉)道」 「西 こがね(小金)道」と刻まれており、道標を兼ねていた。 昭和63年12月指定 | |
| 【市指定文化財】 駒形大明神(こまがただいみょうじん) | |
|---|---|
鎌ケ谷3-3 (詳しい場所はお問い合わせ下さい) | |
| 【市指定文化財】 清田家の墓地(きよたけのぼち) | |
|---|---|
| 鎌ケ谷3-3 (詳しい場所はお問い合わせ下さい) 清田家は江戸幕府の命をうけ、小金・下野牧の牧士役を13代にわたって世襲した。牧士は野馬の管理を行ない、野馬捕りや将軍の鹿狩りの際には、勢子人足たちを指揮した。また、苗字帯刀の他、乗馬や鉄砲の所持も許されていた。 昭和48年10月指定 | |
| 【建造物】 鉄道連隊建設の橋脚(てつどうれんたいけんせつのきょうきゃく) | |
|---|---|
| 東道野辺6-9 アカシヤ児童遊園内に所在する。明治40年(1907年)に津田沼に置かれた陸軍鉄道第2連隊は、昭和初年に訓練用として、津田沼・松戸間に鉄道を敷設した。これはその線路の橋脚である。路線は第二次世界大戦後、現在の新京成電鉄に払い下げられたが、訓練用に敷設された路線のため、大きく曲がりくねっていたので、手直しがされた際に路線とならず、橋脚だけが残されたものである。 | |
| 【市指定文化財】 道標地蔵(どうひょうじぞう) | |
|---|---|
| 南鎌ケ谷3-6-43 行徳・鎌ケ谷・木下を結ぶ「木下街道」は江戸時代の重要な交通路であった。この道標地蔵は、木下街道から神保(現船橋市)への分岐点に建てられたものと考えられるが、現在は清長庵内に所在する。前面には「いんざいみち かしま道なり」、左側面に「かまがい道 施主かねこ」、右側面には「じんぼう道 施主金子」と刻まれている。正徳5年(1715年)に造立された銘があり、市内最古の道標である。 昭和60年9月指定 | |
| 【市指定文化財】 大仏板碑(だいぶついたび) | |
|---|---|
中央1-8-31(郷土資料館) | |
| 【市指定文化財】 錦絵「貴婦人の図」(にしきえ「きふじんのず」) | |
|---|---|
個人蔵 |
|
| 【市指定文化財】 版画集「子ども遊戯風俗」(はんがしゅう「こどもゆうぎふうぞく」) | |
|---|---|
個人蔵 |
|
| 【市指定文化財】 庭訓往来三月之部(ていきんおうらいさんがつのぶ) | |
|---|---|
個人蔵 | |
| 【市指定文化財】 渋谷総司書簡(しぶやそうじしょかん) | |
|---|---|
個人蔵 | |
| 【市指定文化財】 初富開墾(はつとみかいこん)関連資料 | |
|---|---|
中央1-8-31(郷土資料館) |
|
| 【国登録有形文化財(建造物)】 澁谷(しぶや)家住宅(主屋、米蔵、門) | |
|---|---|
中佐津間一丁目地先 | |
| 【国登録有形文化財(建造物)】丸屋(丸屋、丸屋離れ) | |
|---|---|
鎌ケ谷四丁目地先 |
|
| 国登録有形文化財(建造物) | ||
|---|---|---|
| 名称 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
生涯学習部 文化・スポーツ課 文化係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎5階
電話:047-445-1528
ファクス:047-445-1100